「旅するように暮らす 暮らすように旅する」──
それは、私が長く追いかけてきた生き方です。
日常の暮らしでは、モノを手放し、心を軽くして、目の前の時間を旅するように味わってきた。
けれど、土地とつながり、エネルギーを交換しながら“暮らすように旅する”という次の段階は、まだ実現していませんでした。
そして今──10月、
満ちてゆくエネルギーの流れの中で、伊勢志摩という地が呼びかけてきたのです。
「おてつ旅」という形の仕事&ライフスタイルがあることを知り、
これならたくさんのお金を貯めてからでなくても、すぐに実現できる!
お手伝いをすることでその土地の方に喜んでもらいながら、旅を楽しめる!
地域貢献と自己実現の両軸が完成する生き方。
そんな即断即決をして、
リゾートホテルに滞在しながら、その土地の仕事・人・空気と交わること、
観光では決して触れられない“生きた循環”の中に身を置く体験が始まりました。
そこで感じたのは、「経済」でも「仕事」でもなく、
人と場所、想いと行動がつながる“Web5的な暮らし”のリアルな手触り。
この伊勢志摩ワークステイを通して、
“生きたエネルギーを言葉に変える”という、私の根幹が再び息を吹き返しました。
あなたの中にも眠る“循環の感性”が、
この記事を通して少しでも動き出すことを願って──。
体験が信頼に変わる──伊勢志摩での循環の始まり
情報があふれるこの時代、ただ「発信する」だけでは心に届かない。
これから価値を持つのは、体験から生まれたリアルなエネルギー──
つまり、Web5的にいえば「自分という存在そのものが信頼データになる」発信。
伊勢志摩でのワークステイでは、仕事も暮らしも境目はありません。
朝は海の音に包まれ、
昼は地域の人と語らい、
夜には言葉を熟成させる。
その時間のすべてが、わたしの中で“信用の物語”として積み重なっていく。
Web5が描く世界では、信頼や共感が経済を動かします。
つまり、わたしの感性や行動の一つひとつが、新しい通貨のように循環していく。
そんな感覚を、この土地の静けさの中で確かに感じています。
言葉を磨くことは、信頼を育てること。
この伊勢志摩で生まれるひとつの言葉が、誰かの共鳴を呼び、
また次の“わたしの仕事”を形づくっていく──
その循環こそが、Web5時代の働き方の原点なんだと思うのです。
「稼ぐ」と「受け取る」の境目が溶けていく
伊勢志摩でのワークステイ中、仕事と暮らしの境目がほどけていくのを感じています。
朝は海からの光に包まれながらPCを開き、
昼は地元の方と語らい、
夜はその日の体験を文章に落とす。
──その流れ自体が“仕事”になっている。
ここでは「稼ぐ」というより、“受け取る”という感覚が近いです。
共鳴が生まれた分だけ、自然と循環が起きる。
収入はその結果でしかない。
このスタイルには、まさに“存在給”という考え方がしっくりきます。
誰かの役に立とうと力むより、今ここに在るエネルギーを丁寧に表現すること。
そのあり方が、信頼や共感という形で返ってくる。
Web5的に言えば、それは個人の存在が経済のノードになる働き方です。
本業とは別軸であっても、地域に関わる時間が「生き方のミッション」に重なるのです。
地元スタッフとの何気ない会話が、単なる旅では得られない“地に足のついた仕事観”を育ててくれます。
身体のリズムに合わせて働くと、言葉も整う気がします。
Web5時代の豊かさとは、
そんな内的調和が外の循環を生むプロセスなのかもしれません。
伊勢志摩という土地が持つ“発酵のエネルギー”

この土地には、時間をゆっくりと熟成させる力があります。
海と里山、
人の営みが絶え間なく循環し、自然と呼吸を合わせていて、
ここで過ごすうちに、言葉になる前の“気配”──
潮の匂い、朝の光、会話の間合い──が、心の奥に静かに沈殿していきます。
休日に訪れた伊勢神宮は、観光客でとても賑わっていました。
けれど「また来週でも行ける」と思えた瞬間、
旅人ではなく“この地に暮らす人”としての感覚になれます。
そんな小さな意識の変化が、私にとって、「暮らすように旅する」という生き方を選択できている喜びを感じます。
市場で交わす言葉や、宿の隅での雑談が、
心の発酵菌のように私を柔らかくしてくれるのです。
Web5的に言えば、これも場所との共鳴データ。
土地や人との相互作用が、こうしてブログで発信することで、私の中に“新しい信頼のコード”として書き込まれていくのです。
伊勢志摩の静けさは、発信よりも“受信”を教えてくれるような気がします。
この地で生まれる言葉は、考えて作るものではなくて、
ちょっと大袈裟に言うと、自然に湧き上がる“生命の証言”なのかもしれません。
熟成していく「生きた言葉」たち
書くことは、発信ではなく発酵に近いのかもしれません。
体験の中で感じた微細な気配──温度、匂い、間──を観察メモとして残し、少し寝かせる。
その熟成の時間があることで、言葉が“生きもの”として立ち上がってくる。
焦らず、発信前に心の中で育てること。
それが私の“生身の周波数”を持つ文章になるのです。
Web5的に言えば、それはデータではなく、共鳴としての信頼を育てるプロセス。
AIやSNSに届ける前に、まず自分自身がそのエネルギーを味わい尽くすことが、結局は最も届く文章になる。
ブログを書く意味もそこにあるように思うのです。
日々の体験を意識的に味わい、その感覚を文章に変えることで、自分の中の流れが整っていく。
意識するしないに関わらず、“生きているエネルギー”がキャッチしてくれるのを感じる。
誰かに響かせようとせず、ただそこに置く。
それが巡り巡って読者の信頼に変わる──
そんな循環のリズムこそ、Web5時代の「言葉の経済圏」のあり方だと思っています。
Web5的に言葉が信用・価値へ変わるとき
Web5の世界では、ただ文章を書くこと自体が価値になるのではなく、その言葉が個の存在や体験を信用に変えるプロセスが重要です。
ブログやSNSで発信する一言、一つの会話、イベントでの小さな交流──
それらが、仕組みの中で「信用台帳」に記録され、見えない価値として積み重なっていきます。
“存在給”や“共鳴で上がる報酬”という概念も、結局はこの信用の循環を言語化したものだと思っています。
先に成果や報酬を求めるのではなく、まず自分の存在が周囲に与える影響を丁寧に観察し、発信することが軸になるのです。
伊勢志摩でのワークステイでも同じです。
朝の挨拶、宿での雑談、地元の市場での会話──
些細なやり取りが、後で文章として形になり、共鳴として返ってきます。
Web5的には、それは単なるデータではなく、存在と信頼が重なった新しい通貨のような価値。
言葉を丁寧に紡ぐほど、その信頼は自然に循環し、見えない資産として自分の中に積み上がっていきます。
awabotaとつながる循環 〜場が言葉を受け止め、還す場所になる
awabotaは、言葉を単に消費する場ではなく、循環させるコミュニティです。
伊勢志摩で受け取った体験やエネルギーを場に還すことで、言葉は信頼に変わり、次の実践を生みます。
Web5的に言えば、個の存在が場と共鳴し、信用という形で価値を循環させる仕組みがここにあります。
具体的にはこうです。
まず投稿することで、自分の考えや体験を場に置く。
すると他の参加者との対話や反応が生まれ、そのエネルギーを受け取ることで、次の小さな仕事や協働が生まれる。
たとえば、伊勢志摩のワークステイで得た気づきを投稿したら、別のメンバーがそれをシェアしてくれて、私とはまったく繋がっていない人へと流れていく。
川のように次々に流れていき、また自分にフィードバックとして返ってくる。
この循環の中で、言葉は単なる情報ではなく、信頼と価値のコードとして成長していくのだと思えます。
体験と発信がつながり、場と個が互いに育ち合う。
awabotaは、言葉と存在が共鳴し、価値として循環する「Web5時代の実験場」。
呼吸するように、生きた言葉を循環させる
伊勢志摩で過ごしたワークステイは、単なる旅ではなく、自分の存在が仕事や言葉、信用として循環する体験そのものです。
朝の海風や里山の静けさ、地元の方との何気ない会話──
そんな日常の一瞬ひとつが、私の中で言葉となり、やがて読者や仲間の心に届く“生きたエネルギー”へと変わっていく。
Web5的に見れば、文章や発信は単なる情報ではなく、個の存在が信頼や価値に変わる通貨のようなものです。
投稿、対話、小さな協働を通じて生まれる共鳴は、
目に見えなくても確実に積み重なり、自分と場の両方を豊かにしてくれるのです。
この感覚は、“稼ぐ”ことと“受け取る”ことの境目が溶け、存在そのものが循環する喜びです。
そして、私にとってのawabotaはその循環を支える場。
ここでは言葉が消費されるのではなく、受け取られ、還され、信用として積み上がっていきます。
その過程は、私にとっての“存在給”の実践であり、暮らすように旅する生活の延長線上にあるのです。
もしあなたも、言葉や体験を循環させ、自分の存在を価値に変える体験をしてみたいのなら、ぜひawabotaプロジェクトへ。
公式LINEから最新の情報や参加案内が届き、
無料Zoomセミナーで具体的な実践方法をお伝えしています。
ここから始まるのは、ただの発信ではなく、息づく言葉と信頼の循環。
あなたという存在が、この場で生き、還り、価値として循環します。
それこそ、あなたが望んできた本当の生き方かもしれませんね。







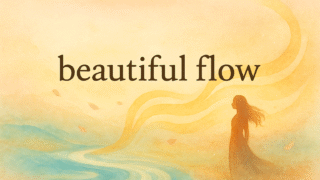














コメント